佐藤有華作品 [つくる前]

稽古が始まる3日前に実施されたインタビュー。佐藤さんがダンスを続けている理由や、大学の卒業制作作品のこと、今回の作品や出演ダンサーについてなど、話題は多岐に渡りました。特に、今までに印象に残ったダンス作品談議に花が咲き…。

- 高嶋
- まず、ダンスを始めたきっかけについてうかがえますか。バレエを最初にされていたとのことですが。
- 佐藤
- バレエは、4歳ぐらいの時、仲のいい幼稚園の友達が習っていて、私もやりたいって真似っこしたのがきっかけです。衣装が可愛いとか、そういう子ども心のあこがれがあったんだと思います。そうやって始めて、住む場所が転々としながらも、バレエだけはなんとなく続けていました。場所が変わる度にその都度先生がコロコロ変わるので、そんなに真面目に基礎を固めて行ったという感じでもないんですけど、とりあえず。中学・高校では部活が忙しくて週1行くか行かないかだったり、受験で長い間休んだりしたこともありますが、結局高校三年生まで続きました。
それから京都造形芸術大学舞台芸術学科に入学しました。私が在籍していたのは演技演出コースだったんですけど、1回生の時は併設されていたダンスコースの基礎の授業も必修だったんですね。そこでコンテンポラリーダンスに出会って、じりじりとはまっていきました。 - 高嶋
- 演技演出コースにいたということは、当初は演劇に関心があったんですか?
- 佐藤
- 関心というか…。私、高校の途中から引きこもってて、勉強しなくなったんですよね。でも、大学には行っておかないと、っていうのもあり、でも、これ以上勉強をがんばれないなとも思っていて、じゃあいわゆる勉強とは全く別の方向に行こうかなと。それで役者とかを調べていたら京都造形芸術大学が見つかりました。
- 高嶋
- その時に、演劇を観にいく習慣はありましたか?
- 佐藤
- ありませんでした。劇団四季のライオンキングを修学旅行で観たことがあるぐらいで。
- 高嶋
- 思いきった進路選択だったんですね。
- 佐藤
- その頃は、なんとか大学に行かなきゃってことと、地元の宮城からも離れたいっていう気持ちが強かったですね。
- 高嶋
- 必修の授業で出会ったコンテンポラリーダンスには、どういうおもしろさを感じましたか?
- 佐藤
- 衝撃を受けたとか、自分にはこれしかないってビビッときたというような経験ではないんですが、やっている内に、なんとなくダンスというのが自分の隣にずっとあるようなものなんじゃないかって感覚になってきたんですね。そうやって、すぐに化学変化が起きるっていうよりは、じっくりじっくり変化して、ちょっとずつ惹かれていった。たとえば、恋人と付き合うような、ちょっと劇的で、一緒にいて楽しいとか嬉しいってなるじゃないですか。勢いもあるし。でもそういう感じじゃなくて、むしろ、結婚相手と、毎日楽しい嬉しいっていうことではなく、でもずっと隣にいるっていう感じに近いというか。

- 佐藤
- さっき、演劇が勉強できるから大学を適当に選んだって言ったんですけど、もうひとつの理由を思い出しました。高校三年生の時、学校には行っていなかったんですが、またバレエに通っていたんです。で、その年の終わりごろ、発表会の時に機会をもらって、初めてソロのバレエを自分で振付して自分で踊りました。だから、自分の進路を考える時期と振付して踊るという時期が重なっていたんですね。私はバレエがすごい下手だったから、自分自身がダンスに関わる進路に進むとは考えていなかったんですけど、踊りを続けたい、離れたくないという気持ちもあった。京都造形大にはダンスコースもあって、その授業も履修できるシステムだったので、ここに来ればなにかのかたわらダンスができるというのも、大学を決めた重要なポイントでした。
- 高嶋
- 大学に入った後も、小作品や、課題を与えられて作るというようなことはあったんでしょうか?
- 佐藤
- ありました。2回生では授業発表の公演も経験しました。
- 高嶋
- そして昨年、卒業制作では『Cardinal Line』という作品を上演された。どのくらい時間をかけて作ったんですか?
- 佐藤
- 9ヶ月ぐらいでしょうか。
- 高嶋
- 映像で拝見して、無機的で静かなんだけれど、挑発的なところがある作品だなと思って、とてもおもしろかったです。作品の構成として、出演者の6人という数もすごく計算されてますよね。1人か2人だけだったらダンサーそれぞれの個性や身体性に目が行ってしまうけれど、6人というのはとても微妙な数で、あるシーンでは集団に見え、あるシーンでは個々に見えるという、個人の身体と集団性のあいだをどっちつかずで行き来している感じがしました。あの作品について、佐藤さんがどういうことを考えていたのかお聞きしたいのですが。
- 佐藤
- 人数に関しては、ダンサーを決める時にオーディションをやったんですが、当初すごく迷っていました。あの6人とも、身長も体型もぜんぜん違う。でも、そのバランスを考えた時に、1人でも抜けるといきなりアンバランスになってしまうんです。バラバラなのに、6人揃うとはまるバランスがあって、それであのメンバーになりました。 作品を作っている時に考えていたのは、わたしは基本的に物語のようなものを作品につけたくないと思っていて、いかにそういった物語の色や土台がない中で、身体本来の色やリズムを感じてもらえるか、というのが軸にありました。
- 高嶋
- 身体本来のリズムというのは、ダンサーによって出し方が違うと思います。そのあたりは、どのように指示を出していったんでしょうか。
- 佐藤
- 個々のリズムを活かしつつ、同じ空気にいるというようなことを考えていました。身体の質感を合わせるために、一対一の稽古で振付をしていきました。だから、振付は一人ずつ全員違うんですね。たとえば、全然違う身体に同じ振付をしたら、その違いが目立ってしまうけれども、同じコンセプトで違う振付をつけたら、同じ様に見えるんじゃないかって思ったんです。あと、メトロノームを使って、物理的に速度というものを考える稽古をやって、私がイメージする身体の質感が見えてくる速度を共有していくような作業もしましたね。 がむしゃらに練習して筋力をつけていくようなやり方ではなくて、身体の中の、たとえば背骨と手足がどのように繋がっていて、どうすれば腕がこう動くのか、というような、全身のつながりと機能を意識しながら作っていました。その人自身の身体の動かし方によって、動きの質感が変わっていくので。アレキサンダーテクニックの先生にグループレッスンをしていただいたこともありました。

- 高嶋
- お話を聞いていて、出演者との丁寧なコミュニケーションが必要な作品づくりをされていると感じました。それは、バレエの発表会でソロの作品をつくった時とはまったく違う作り方だと思うんですが、いかがでしょうか。
- 佐藤
- たしかに、かなり違うと思います。昨年、卒制と並行して短いソロの作品を作っていたんですが、その時は自分の中でストーリーのようなことを自由につけてやっていたりもして。でも、他の人と作品を作るときには、集団や、社会といったことを意識して、ソロの時よりも広い意味で捉えているような感覚がありますね。
- 高嶋
- 卒業制作の時は振付に専念されていたようですが、自分が出演するという考えはなかったんでしょうか?
- 佐藤
- 2年前に自主企画で初めて大きな作品に取り組んだ時は、演出も出演も兼ねていたんですけど、二つの立場の視点が移り変わるのがすごく難しくて。演出の作業がおもしろくて、試したいことや時間をかけてやりたいことがいっぱいあるけれど、ダンサーとしての仕事もあって、演出に集中できなかったので、卒業制作では出演をしないことにしました。
- 高嶋
- 自分自身が踊るのが大好きで、それで満たされるっていう人は、おそらくソロは作るけれども、他人を振り付けるということに喜びをあまり感じないのではないかと思います。で、佐藤さんは、もちろん踊っている時の喜びもあるんでしょうけど、踊っている人を外側から見たいっていう欲求があるから、『Cardinal Line』のような作品になるのかなと思いました。
- 佐藤
- 外から見るのっておもしろいですよね。踊りって、そのひとの根本的なものをうつしだすものだと思っているんです。その人自身の性質とかを言葉ではなく感覚的にキャッチできる楽しみだったり、身体の動かし方一つ一つに詰まっているその人自身の経験の積み重なりを分析したりすることも楽しいですね。

- 高嶋
- 今回のねほりはほりではどういった作品になりそうですか?
- 佐藤
- 『Cardinal Line』の延長でやりたいと思っています。物語やテキストというものを使わず、無駄なものを省いた状態で、身体自身がどういった時間を過ごすのか、どういった時間を流していくのかということをやりたい。作品を作るときには、たとえば片足を曲げるとか貧乏ゆすりっていうような動きのモチーフがあって、そのひとつのかたちの中から可能性を探していくのですが、今回はそのモチーフとして、引っ張る、という動きを考えています。まだ、言葉にしてもなかなか具体的にならないんですけど…。あとは、呼吸を音として使ってみたいということがあります。基本的には無音が好きなんです。というのも、身体が動いた時に音が出てくるじゃないですか。その音に少しでも耳を傾けてほしいということがあって。呼吸の音やリズムがそれぞれ出演者3人バラバラにありながらも、その呼吸の時間が動きとも重なって行ったら面白いかなと、まだ稽古前ですが、考えています。
- 高嶋
- 出演する3人とは、これまで一緒の作品に関わった経験はありますか?
- 佐藤
- ないんです。中間さんとは少ししゃべったことがあったんですが、川瀬さんと正木さんは踊っているところを見たこともなく、面識もありませんでした。たまたま3月の後半に3人がそれぞれ別の作品に出演していたのでそれを観に行って、あ、こういう人なんだな、と。
- 高嶋
- 今の段階で、出演者それぞれにどういう印象を持っていますか。
- 佐藤
- まず、正木さんが背が高くて、中間さんと川瀬さんが小柄、このバランスがどうなるかなって思っています。男の子も一人だけだし、どういうアンバランスなバランスみたいなものが見えてくるのかなって言うのはおもしろいところだなと。
ひとりひとりに関して言うと、中間さんは、派手な印象ではないんですけど、自然と目が行ってしまうような不思議な魅力のあるダンサーだなと思っています。舞台に立った時の姿から、彼女なりの舞台や踊りへの意思を感じて、それが存在感につながっているのかなと。もちろん、振付家や作品ごとによって立ち方も変わるんですけど、彼女自身が持っているものってもっとなにかあるんじゃないかなと、ものすごく興味を持っています。
川瀬さんは、身体のラインがはっきり見えて、空間に対しての線ということがとても見えやすくて、可動域も広い。先日、川瀬さんが演出振付をした作品を見ましたが、おそらく彼女が舞踏出身ということもあって、空間に対する視点を持っている踊り方をする人だなと思いました。彼女には空間が見えていて、かつ、空間とコンタクトもとっている。その感覚って、持っていない人はまったく持っていないんですよね。
正木さんは、その時の作品を見た限りでは、多くを受け取る事は出来なかったのですが、その中でも、ちょっとした動き、一瞬一瞬に、はっとさせられる瞬間がいくつかあって、これはなんだろう、この人は何を持っているんだろうっていうことにすごく可能性を感じています。

- 高嶋
- 今まで見た作品の中で、これがよかったなとか、あるいは自分もこういう作品を作ってみたいなとか、あるいはこういう作品だったら出演してみたいなっていう作品はありますか?
- 佐藤
- いくつかあります。ひとつめは、KYOTO EXPERIMENT 2013で上演されていたマルセロ・エヴェリン『突然どこもかしこも黒山の人だかりとなる』です。繊細な空気感と洗練された感じというのがすごく好きで…。きれいだなって。
- 高嶋
- きれいというのは、どのあたりのことを指していますか? ダンサーの動きだったのか、作品から受けた感じなのか。
- 佐藤
- ずっと動き続けて、時間を蓄積し続けた末の瞬間の身体というか…自分とは別の時間を生きている生き物でありながら、それでも生きているものであるという感じでしょうか。人工的なきれいさではなく、存在っていうものがきれいだなあって…伝わったでしょうか。高嶋さんはあの作品を見ましたか?
- 高嶋
- 2度観に行って、それぞれ感触が違いました。作品中でもいろんなフェーズがあって、ひとつずつ感じたことがすごく違う。一言でこれだって示せないですね。色んな感覚を味わったあとに、すごく至近距離で見つめ合っているにもかかわらず、ものすごく遠いところにいるんだよって突き離されて終わったような、体験の密度がすごい作品でした。
- 佐藤
- たしかに、そうですね。開演した時点でのあの出演者たちの在り方と、最終的に辿りついた在り方のギャップは、かなりあったように思います。すごく印象に残っていますね。
- 高嶋
- ほかにもそういう作品はありますか?
- 佐藤
- またKYOTO EXPERIMENTなんですけど、2012年に来ていたリア・ロドリゲスの『POROROCA』。すごくきれいだなと思った瞬間がありました。とっちらかっている雰囲気のようでいて、色が非常に厳選されている、ノーマルな状態で身体を見ることが出来るような作品でした。マルセロのもそうだけれど、ひとつ洗練された軸が通っている空気感というのが好きで、自分もそういう作品を作りたいと思いますね。
それから、寺田みさこさんの『アリア』も印象に残っています。すごくピンポイントなんですが、冒頭でダンサーがぶるぶる震えていて、ある瞬間に全員が揃って足をあげるところがあって、そこがすごくよかった。寺田さん自身がストーリーやいろいろな色を入れることが得意な人で、私が目指しているものとはちょっと違うんですけど、演出家が自分の追求している身体への価値観を見出して、そこに向かって物語が進んでいくところがとてもいいなあって。
あと、山田せつ子さんの作品で拝見している『Blanc ササヤイテイル ツブヤイテイル』と『Dance あけて、しめて、あけて』のふたつ、どちらもすごく気に入っています。『Blanc ササヤイテイル ツブヤイテイル』は美術家とのコラボレーション作品だったんですが、その美術が、その空間を支えているご神木のような役割を果たしていたように思いました。美術が、静謐な空気感を作り出している。そこに立ち会っていること自体が、神社やお寺の中にいるような感覚というか。『Dance あけて、しめて、あけて』では、せつ子さんのソロが印象的でした。長く踊りを続けている方だから当たり前なのかもしれませんが、自分が踊ること、この場にいることに対してものすごく強い意志を持っていて、その意志が身体そのものにあらわれていて。そういった強いものにあこがれるというか、いいなあって思いました。
佐藤有華作品 [つくっている最中]

インタビュアーの高嶋さんが佐藤さんの稽古場を見学してからインタビューを行いました。
稽古の中で行われた動きを、佐藤さんがどのように見ていて、高嶋さんはどのように感じていたのか。
佐藤さん特有の稽古での言い回しなども、ひとつずつ解剖されていきます。

- 高嶋
- 稽古前半は、1つの単純な動きを、ダンサーひとりずつ、かなりしつこくやっていましたね。その同じ動きをもとに、ふたつの感覚の違いというのを試していた。ひとつめは周りの音を聞きながら。ふたつめは自分の身体の音を聞きながら。意識の持ち方で身体の動きがどう変わるかっていうことの試みだったと思うんですが、私には、すごく変わったなって見えた瞬間と、あまり変わらないという瞬間があったように感じられました。でも、佐藤さんは毎回違うというようにコメントされてましたね。その違いは具体的にどういうものなんでしょう?
- 佐藤
- そもそも、そのふたつの意識の違いそのものがやりたいというわけではないんです。シンプルな動きをやろうとした時に、ただ動かすだけだと身体が粗いんですね。走っているのと同じような運動に見えてしまう。そうではなくて、動くことによって身体の本質的な音みたいなものが聴こえてきたらいいなって思っていて、そのための実験としてやっています。実際は毎回やるごとにすごく大きく変化が生まれているわけではない。でも、自分が近づこうとしていることは、とても微妙なところにあるから、わずかな変化もひとつひとつ拾っていきたいんです。意識するところを変えたら見え方がどう変わったか、ということを、ダンサーと何度も意思疎通をはかることで、ダンサーの引出しが増えて、選択することができるようになるのではないかと思うんです。それから、ひとつひとつの変化は些細でも、たくさん重なっていくとすごく大きな違いになっていく。その小さなことを溜めていくような作業をやっている気がします。
- 高嶋
- 身体の音を出すっていうのは、たとえば関節をバキバキ鳴らして物理的に音を出すということではなくて、比喩的な音ということですよね。音って目に見えない。佐藤さんが振付家として求めていることは、フォルムではないんだろうと思います。音という聴覚の比喩で表現されているのがおもしろいですね。この比喩についてもうちょっと知りたいんですが、違う表現で言い換えるとしたらなんでしょう。
- 佐藤
- 身体の音じゃなかったら…うーん、なにか別の言葉が見つかるといいんですけど。ダンサーに伝える時にも。
- 高嶋
- 音楽じゃなくて、音。音楽というとメロディーがあって流れがあって、つかまえやすいですけど、音はまた違いますよね。
- 佐藤
- そうですね…。少し話は逸れますけど、先日、春秋座で観た笠井叡さんの『今晩は荒れ模様』について、「踊りが振付に見えなくて、ダンサー自身がそのまま出ているように感じた」という感想を高嶋さんから聞きました。そういうふうに、身体が勝手にというか、必然性の中で動いていく。あの笠井さんの作品では、身体がまるごとひとつの全体として、身体自体がどう動きたいか欲求を持っているような印象がありました。それと比べると自分の今回の作品は、身体をまるごとひとつとして捉える前に、手や足といった細分化されたパーツがそれぞれ欲求を持っていて、それが一つの身体と言う入れ物の中にいる状態が見たい、と思っています。それを音と呼んでいるというか…。パーツひとつずつが空間や自分自身とコミュニケーションをとる、会話する。
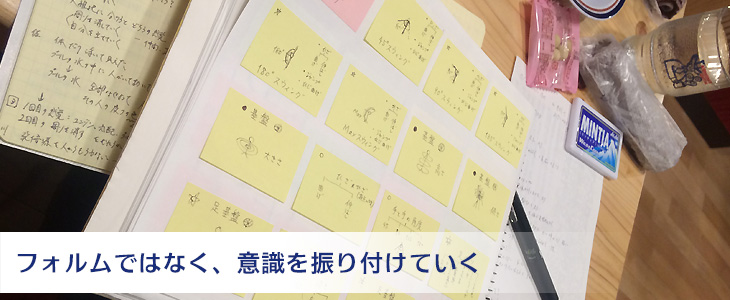
- 高嶋
- 稽古を見ていて印象的だったのは、ある人がやった意識の仕方を別の人が真似しようとしても、しっくりこなくて、あまりおもしろくない。でも、別の意識を持とうとすると、よくなる。同じ言葉で動機付けしてもうまくいく人といかない人がいるというのはおもしろかったですね。作品として整えていく時に、たとえばダンサーが同じ動きをするけど3人がそれぞれ違う大きさや高さの音を出して和音のように分散させるのか、あるいは動きはバラバラなことをしているようだけれど音は同じ質感に合わせてチューニングしていくのか、どういった方向でやっていくのでしょう?
- 佐藤
- そこが問題なんです。もともと土台にある『Cardinal Line』のコンセプトとしては、バラバラな身体がハーモニーになったり、違う音を出しているはずなのに波形が一緒で同じように聴こえるようなことがおもしろい、というところにあるんです。同じドの音程でも、楽器が違えば違う音として聴こえるようなおもしろさ。でも、今回の出演者と対面してみると、男女も混ざっているし、身体が全然違うんですよね。今まで同じ大学の中でほぼ同い年の、ダンスに興味を持っている女性と一緒にやっていた中で感じていた個々の違いとは比べものにならないぐらい。それに直面した時に、たとえば違う楽器をうまい具合に配置や動きをチョイスして同じ風に見えるようにすることはできるかもしれないけれど、それになんの意味があるんだろうと考えたんです。自分のやりたいことが、その先にどういう発展をしていくのか、というのを今は探っている段階ですね。
- 高嶋
- 一般的にダンスの振付というのは身体の動きをつけることだと思われていますが、今日の稽古を見ていると、実は身体でなく意識を振り付けることなんじゃないか、と感じました。足をこの高さまで上げてくださいというような物理的な指示ではなく、意識の方にアプローチしていく。
- 佐藤
- そもそも、動きを具現化していくのを自分から決めてしまうこと、その空間での時間を生きるのはそのダンサー自身の身体なのに、私の言葉を渡してしゃべれっていうことに違和感があるんですね。英語を練習して上達するようにいずれぺらぺらしゃべれるようになるのかもしれないけど、それぞれの身体はもともと母国語を持っていて、その身体がその身体でしかしゃべれない言葉を持っているって考えた時に、この作品の言葉は英語だから強制的に全員英語をしゃべってねっていう筋の通し方もあるんだろうけど、それぞれの母国語をしゃべりながらもコミュニケーションをとれるような方法がないかなって考えています。

- 高嶋
- その身体が持っている母国語というのは、なぜ人によって違ってくるんでしょうか? 体格や性別、ダンスの経歴、癖などいろいろ要素はあると思うんですが、どのあたりに大きく違いを感じますか。
- 佐藤
- おそらくひとつには、身体のバランスがあります。身長とか癖といった、物理的な情報。今までの生活や環境といった外的なことによって形成されたことが具現化されているようなものたちです。 もうひとつには、その身体がもともと持っている、土台の部分というか。たとえば、さびしがり屋とか元気で明るい人とか、そういった性質っていうのは、全員がすべての成分を持っている上でそれぞれのパーセンテージに差があるっていう、バランスの問題だと思うんですよ。その成分を全部剥いていった時に、その成分が乗っかっていたその人の土台があるんじゃないかなと、興味を持っていて。そこからは、今受け取っているものとは違う、単純に言葉では説明できないようなものを受け取れるんじゃないかと思っているんです。 今話をしていて気付きましたが、自分が稽古でやっていることは、身体の動きから出てくるその人らしさを逃れようとする一方で、その人にしかない母国語のようなものを聞こうとしているっていう、ある意味矛盾したことなのかもしれません。
- 高嶋
- 佐藤さんの作業が身体のフォルムへの振付ではなくて意識への振付であると考えた時に、出演者がダンサーである必然性はどのくらいあるんでしょう? 可動域の広さや柔軟性が必須というわけでもないですよね。ダンサーではない、ふだん身体にあまり意識をはらっていない人ではできないんでしょうか。
- 佐藤
- 人は日々無意識に身体を動かして生活しているじゃないですか。無意識であるということに気づくというのは本当に難しい。その、気付きにくいことに気付く柔軟さがあるということは必要だと思っています。ダンサーっていうのは、踊りに自分なりの価値や魅力を感じている人たちで、身体や空間に対する感覚の目を持っていると思うんですね。今の稽古でも、見ていて分かりづらいとは思うんですが、私が投げかけた言葉に対してかなりダイレクトに影響を受けて変化しているんです。でも、そもそも存在自体を認知出来なかったら、はじまる事すら出来ないと思うんですね。
- 高嶋
- 稽古の後半でやっていたワークは、私にも変化がかなり感じられておもしろかったですね。3人が三角形をつくって向き合って座って、いくつかの動きを元にそれぞれがバリエーションを出していく。最初は他の人の気配や周りを意識しながらやっていて、その時は見ていてすごく心地よかったというか。バラバラなんだけれども、3人が共有しているものがあって、空間に一緒になじんで呼吸している感じがしたんですね。その次に、周りを遮断してください、という佐藤さんからの注文がありました。そうするとまったく印象が変わって。さっきの繋がりはなんだったんだっていうくらいに、個々がバラバラで空間にいたように感じられました。それに対する佐藤さんの感想もまたおもしろくて、最初は水の入ったプールに3人が入ってやっているように見えたとおっしゃっていた。つまり、1人が水しぶきを起こしたら他の人が影響を受けるということですよね。そして、周りへの意識を遮断した時は、水が抜けてしまったプールの中のように思えたと。水があるっていう捉え方と、それが満たされているのと空っぽの状態がこんなに違うんだというのが興味深かったんですね。

- 佐藤
- 空間がプールというか、水槽だとして、その中に水があるっていう状態が今日の稽古だったとすると、その水を霧にしたり、風にしたり、あるいは粘土だったり、そうやって身体によって空間の中身を変えていくということにも興味を持っています。空間をそうやって変えていくためには、ただ身体の形を振りつけても意味がなかったから、意識を変える、意識を振り付けるという方法になっていっているんじゃないかな。
- 高嶋
- 空間っていう言葉が出てきましたが、稽古の中で何回も「空間にはまる」っていう言い方をされてましたよね。どういうことを言いたいのかわかりにくかったんですが、ダンサーはあまり聞き返したりしていなかった。稽古の中ではよく使っている言い方なんでしょうか?
- 佐藤
- 初日からずっと使ってますね。でもやっぱり言葉だけ聞いても分からないので、わたしが言う「はまる」っていうことがどんな作業のことかを共通言語にするために必死に稽古しました。
- 高嶋
- さっき言っていたような、水槽に水が満たされている状態を共有するということ?
- 佐藤
- そうですね。でも、それを水とか霧と言わずに、「はまる」って言っています。みんな水の中にいるっていうイメージで踊ることはできるんですよね。それも面白いけど、今回やりたいことは、ここにはないものを頭の中でイメージして作り上げて具現化しようとすることじゃなくて、逆に、ここにあるのに見えないものを見る、それを身体で具現化するということ。 日常に空間はありふれているけど、それが自然だから、私たちは普段ほとんど空間のことを見ていない。それは、空間の中にいるといえばいるけれど、空間を存在させていないような状態だと思うんです。じゃあ、その空間を存在として認識するっていうのはどういうことなのか。その空間にほころびのようなツボを見つけてそこに身体をねじ込んでいくような作業をしつづけた時に行きつく場所があって、その時にようやく自分も含めたその空間と時間があるんじゃないかって思って、それを空間にはまるっていう言い方をしていて……うーん、全然わからないですよね。なんて言ったらいいのか……。
- 高嶋
- ダンサーを見ていて、いまはまっている、はまってないっていう違いが確実にあるんですか?
- 佐藤
- ありますね。踊っている方にも確実にあります。でも言葉にしようとすると、なんとも表現できないというか…。でも、このことをどう感じられるのか、それを模索しているのが『Cardinal Line』ですね。
- 高嶋
- 卒業制作の時も、空間に対して同じ関心を持っていたんですか?
- 佐藤
- そうです。卒業制作の時も、空間の時間をどう流していけるのかをやっていました。見ている人と時間を共有するって言うことが自分の軸になっているんですけど、ただダンサーがここに立っているだけじゃ、時間を共有したことにはならないんじゃないか。空間自体の時間を流すために必要な作業があると思っています。卒業制作の時は、少し消化不良な感じがあって、もっと先が見たくなって今回はそのコンセプトを引き継いでいます。同じく継続している『Cardinal Line』っていうタイトルは、一本の線と四本の手足、つまり身体の基本的な線のことなんですが、タイトルによってあまり意味づけをせず、フラットな状態で見てほしいという主張でもあります。
| 上演作品 | 山本和馬「愛してしまうたびに。」・佐藤有華「Cardinal LineⅡ−1」 |
|---|---|
| 日程 | 2015年 5月30日(土) 17:00 31日(日) 14:00 ※2作品連続上演、30日(土)は終演後にトークセッションあり |
| 場所 | 元・立誠小学校 2階 音楽室 google map |
| 料金 | 1,700円(当日券 +300円) |
| 上演時間 | 30分+30分 |
関連PROGRAM
ARTIST
佐藤有華さとうありは

1992年生まれ、宮城県出身。幼少よりクラシックバレエを習う。2015年京都造形芸術大学舞台芸術学科演技演出コース、首席卒業。卒業制作『Cardinal Line』にて学長賞を受賞。現在、フェルデンクライス・メソッドの資格取得のため勉強中。
INTERVIEWER
高嶋慈たかしまめぐみ
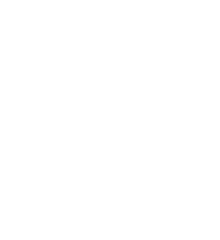
美術批評。京都大学大学院博士課程。「明倫art」(2011~13年)、批評誌「ART CRITIQUE」、小劇場レビューマガジン「ワンダーランド」などの媒体や展覧会カタログにて、現代美術や舞台芸術に関するレビューや評論を執筆。企画した展覧会に、「Project ‘Mirrors’ 稲垣智子個展:はざまをひらく」(2013年、京都芸術センター)、「egØ-『主体』を問い直す-」展(2014年、punto、京都)。


